

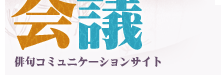
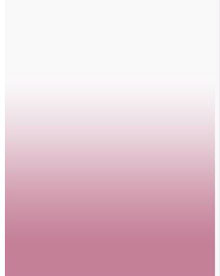
| 白山句会会報 No.36 | ホーム |
| 白山句会 白山句会報第36号 □ 日時 平成30年10月13日(土) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〈 俳 話 少 々 〉 今回は事前調整が付きませんでした。 <以上、伊藤無迅記> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〈 句 会 報 告 〉 *一部作品については作者の意図をそれない範囲で原句表現の一部を改めた句があります。 *また、海紅・勝人選は互選点数に含まれておりません。 ☆ 海紅選 ☆
☆ 勝人選 ☆
☆ 互選結果 ☆
< 了 >
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Copyright ©2025 BASHO-meeting. All Rights Reserved. | このサイトについて |
サイトポリシー |