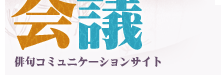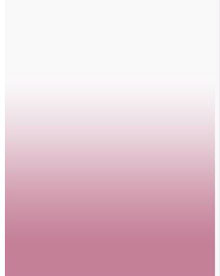〈 句 会 報 告 〉
* 一部の作品については、作者の意図をそれない範囲で原句表現の一部を改めたものがあります。
* 海紅選の句は互選点数に含まれておりません。
☆ 海紅選 ☆
| 両肩に電波塔乗せ山眠る |
ムーミン |
|
|
| 蜜柑剥くなんだか嬉し同い年 |
うらら |
|
|
| 野良猫の流し目熱くブーツ往く |
かずみ |
|
|
| 母逝きて夜目に明るき柊木の花 |
美知子 |
|
|
| 痛みとて生きてる証冬銀河 |
喜美子 |
|
|
| 包帯のごと養生の冬木立 |
梨花 |
|
|
| 冬晴れや笑顔笑顔の草テニス |
ふみ子 |
|
|
| 柿紅葉工具置き場はトタン屋根 |
由美 |
|
|
| 冬霧をヌッと出で来る始発かな |
つゆ草 |
|
|
| ゆるさないコート衿立て駅に立つ |
かずみ |
|
|
|
|
|
|
☆ 互選結果 ☆
| 6 |
篝火も手締めに和する三の酉 |
こま女 |
|
| 6 |
蜜柑剥くなんだか嬉し同い年 |
うらら |
|
| 5 |
両肩に電波塔乗せ山眠る |
ムーミン |
|
| 5 |
薄墨を幾重も流し冬の雲 |
馨子 |
|
| 4 |
痛みとて生きてる証冬銀河 |
喜美子 |
|
| 3 |
犬留守の犬小屋にある冬日向 |
酢豚 |
|
| 3 |
雪催馬の顔もつおしらさま |
無迅 |
|
| 3 |
頬紅を差して冬空目覚めけり |
つゆ草 |
|
| 3 |
煮こぼれて鍋が火を消す雪もよひ |
月子 |
|
| 3 |
師走雨傘さす人とささぬ人 |
しのぶ子 |
|
| 3 |
そぞろ寒マイナンバーの写真撮る |
和子 |
|
| 2 |
包帯のごと養生の冬木立 |
梨花 |
|
| 2 |
ほろ酔の歩みを止めし冬の雨 |
こま女 |
|
| 2 |
冴へる日の夜空に青を残しまま |
うらら |
|
| 2 |
山眠るナウマンゾウを抱きつつ |
由美 |
|
| 2 |
冬めくや俯きかげんの二人連れ |
ふみ子 |
|
| 2 |
冬晴れや遠回りして富士見坂 |
馨子 |
|
| 2 |
霜月やパリが喪にふす日曜日 |
むらさき |
|
| 1 |
矢の如き十年がゆく町小春 |
海紅 |
|
| 1 |
足袋繕ふ教師の母の戦後かな |
梨花 |
|
| 1 |
大冬木待ち人を待つ如きかな |
海紅 |
|
| 1 |
博多帯動けば鳴るよ寒三日月 |
月子 |
|
| 1 |
ゆるさないコート衿立て駅に立つ |
かずみ |
|
| 1 |
しぐるるや熱気伝わる大道芸 |
喜美子 |
|
| 1 |
クレヨンの散らかる如き紅葉かな |
海紅 |
|
| 1 |
子鯨の供養塚あり浜の風 |
梨花 |
|
| 1 |
苑の隅茶亭のくわしは玉菊と |
松江 |
|
| 1 |
納豆を百回捏ねる十二月 |
無迅 |
|
| 1 |
柿紅葉工具置き場はトタン屋根 |
由美 |
|
| 1 |
母逝きて夜目に明るき柊木の花 |
美知子 |
|
| 1 |
片岸に集ひし鴨や風強し |
うらら |
|
| 1 |
鴨九羽空ゆく形や水を切る |
松江 |
|
| 1 |
入日やな間に己が影冬木立 |
憲 |
|
| 1 |
野良猫の流し目熱くブーツ往く |
かずみ |
|
| 1 |
唐人ら御籤ひきをり神の留守 |
憲 |
|
| 1 |
冬茜この束の間の切なさよ |
馨子 |
|
☆ 参加者 ☆ <順不同・敬称略>
谷地海紅、安居酢豚、尾崎喜美子、根本梨花、水野ムーミン、大江月子、中村こま女、鈴木松江、椎名美知子、米田かずみ、平塚ふみ子、宇田川うらら、佐藤馨子、
荒井奈津美、三木つゆ草、伊藤無迅 (16人)
<欠席投句者>
柴田憲、礒部和子、むらさき、大石しのぶこ、西野由美(5名)
<以上、宇田川うらら・佐藤馨子記>
|
☆ 総評 ☆
今回は先生から俳句の形(かたち)に関する話題提起がありました。つまり俳句が俳句たるには、俳句的な形というものがあり、その形がある程度確立されていなければ厳密には俳句とは呼べない。つまり、独り善がりになってしまい、読者(人の理解)を得ることはできないという趣旨のお話があった。
想像するに、先生の今回の話題提起の背景には、選句時に廻された各俳句作品を拝見しての感想と、安居さんの話を聞いた感想から複合して湧いて来たものではないかと拝察する。
つまり通常は、詩的発想で得られた俳句以前のオリジナル・イメージを、俳句性に基づいた型の変換装置を通し俳句作品に昇華するが、その変換装置が十分でないと、俳句にならない。酢豚さんの場合は、能村登四郎という作家作品に惚れ込み、その型を身につけることで自然と俳句というものを会得した。その意味で、好きな作家をもつことはきわめて大切であるということではないかと思う。
筆者個人から見ても、折角詩想豊かな題材を扱っていながら、変換装置が機能していない不完全な表現のために、惜しいと思う作品が幾つか見うけられた。
具体的は、二句一章、一句一章の正しい認識、切れの認識などの俳句特有の表現上の特性を理解し、これを常に心掛けた上で俳句を作ることではないかと思う。
*俳句性:一般に俳句特有の表現上の特性を指す。上述した句の形、切れ、季語の斡旋法、
非観念性、未完結性、無名性…など、俳句が持つ多くの特性の総称として使われることが多い。
<以上、伊藤無迅記>
< 了 >
|