

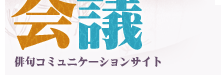
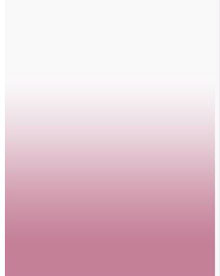
| 白山句会会報 No.10 | ホーム |
白山句会 大宮盆栽村吟行報告 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
☆ 谷地海紅選 ☆
☆ 互選結果 ☆
<宇田川良子・記> ☆ 合評 ☆ 披講後の合評で、句中の「 」(かぎカッコ)が話題にのぼった。先生のお話を要約すると、〈句読点やクエスチョンマーク同様に、近代になって誤読を避ける目的で、親切心から定められた表記法。ただし目上の人に対しては「親切」が失礼にあたることがあるから要注意。俳句は江戸の古式に遊ぶという側面があるから、付けなければ意味不明の場合を除いては不要。作者の判断に委ねてよいだろう。ただし無駄を省くという態度を忘れない方がよい〉。 <尾崎喜美子・記> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 尾崎喜美子・記 > 【大宮盆栽村吟行記】 大宮盆栽村は、関東大震災後、東京駒込の植木職人が盆栽栽培に適した広い土地を求め都下駒込・巣鴨から移住、拓いた場所で、戦後は、欧米諸国にも注目され、今でも年間五千人以上の外国人観光客が訪れる。盆栽職人の住む家々の佇まいは、早くから周囲に気を配る地域協定が行き届き閑静そのものである。盆栽村を歩くと、ほぼ中央に句会場の「盆栽四季の家」がある。 と、紹介されている。盆栽村はJR「土呂」駅・東武野田線「大宮公園」駅周辺の一帯を指す。一般に開放された盆栽園が点在し、庭の入れの行き届いた民家も気持ちが良い。 一村を盆栽にして冴返る ひぐらし 「蔓青園」で倒れかかった盆栽を見つけ知らせると、レインコートを着て水遣りをしていた職人さんが振り向いた。それは、青い目の外国の方であった。句会場の「盆栽四季の家」を確認して、それぞれ盆栽村の探索に出掛ける。シーズンともなれば、多くの人で賑わうのであろうが、さすがにこの季節、行き遇う人も少ない。 句会場の裏にNHK「趣味の園芸」に出演中の山田香織さんが経営している「清香園(せいこうえん)」があり、四、五人が盆栽体験をしていた。建物の前では、職人見習いらしき人が盆栽の雑草をピンセットで抜いていた。ピンセットは目から鱗、ひとつの発見であった。かえで通りを行くと、明治から昭和にかけて活躍した漫画家・北沢楽天の使った道具などを展示した[漫画会館]があった。楽天は日本で最初にカラー漫画を作成した人であると言うことである、知らなかった。それより吃驚(びつくり)させられたのは、何処にも係の人がいないことで、勝手に入り一巡りして又、勝手に出た。しかし、裏庭には気づかず、お散歩マップに載っていた金色のコイを見逃してしまった。残念!! 少し先へ行くと「○○会社」と表示があるが、一見しもたや風の家の庭先に見事な紅梅が咲き誇り、陽だまりには、な、なんとポニーがいたのである。去り難く、しばらく眺めていたが、動く気配もないので句会場に戻ることにした。 「盆栽四季の家」は、18世紀初めに建てられた東角井光臣家の居宅の一部を移築、模写復元したもので、昭和59年(1984年)12月20日に開設されたとある、約30年経っていることになる。なお東角井家は大宮氷川神社の宮司の家柄である。 入口を入ると「たたき」があり、囲炉裏の切られている板の間があるが、火がない。皆が盆栽村の散策から戻り、それぞれ持参したお弁当を広げるが、とにかく寒い。せめて、入口の戸を閉めて風を防ごうとしたら、管理人からクレームがついた。皆、吹き晒しの中で黙々と食べる。京都府綾部から遠来の平岡さんが「京都も寒いけれど、こんなに風の強いことはありまへん」と驚いていたが、いかに関東名物の空っ風とは言え、こんな日も珍しい。 句会場である座敷に入れる時間となり、机を並べて句会の準備が終わり、ストーブが運び込まれると、やっと人心地がついた。かずみさんが用意してくれた熱いお茶が何よりのご馳走で、また添えてくれた加賀名物の栗蒸し羊羹もとてもおいしかった。 今回、かずみさん、無迅さんに下見から懇親会の予約など、何から何までお世話になった。その上、かずみさんは、お茶とお菓子を吟行の間中持って歩いてくれたことになる。 頭が下がる。感謝・感謝である。 句会にはインフルエンザに罹って回復途上、体調の万全でない海紅先生が、駆けつけて下さった。皆「大丈夫かしら」と心配しながらも、先生のいらっしゃらない句会では盛あがらない。矢張りうれしい。先生有難うございました。 かずみさんの言葉通り「春疾風の3字が何度も目に飛び込む句会席、砂塵が舞うほどの悪天候」であったが、参加した皆の心は充分満たされたように思う。決して忘れることのない吟行となった。句会を終えた私達は、懇親会場直行組と氷川神社参詣組とに分かれて行動することになった。 氷川神社は2400年以上前の第5代考昭天皇の時代に創建され、聖武天皇の時代に「武蔵の国一宮」と定められた日本でも有数の神社で、関東一円の信仰を集めている。「大いなる宮居」と称されたのが大宮の地名の由来となっている。 我々は、元神領であった大宮公園を横切って進む。広大な境内は約三万坪もあるという。その昔、母が良く「女学校で一緒だった東角井さんは学校から帰る時に大宮駅から他人の土地を踏まないで、家へ入った」と話していたのを懐かしく思い出す。 そういえば以前、一の鳥居から参道を歩いたことがあった。一の鳥居は中山道との分岐点になっており、埼玉副都心駅から五分位の所にある。一の鳥居から社殿までは、なんと二キロ近くあり、途中まで車道ではないのに車が通っている。車道では無い証拠に、参道に面した家は、道路認定が取れないので参道に対して背を向けて建っているのだ。公園の沼にはオナガガモが泳ぎ、裸の大木には夕暮れ時で、ねぐらに帰ってきたカラスが群がり騒いでいる。何か所もそんな木が有り遠くで聞くその声は「列車の音?」と紛うばかりである。梅園の紅梅が優しい香りを放っている。 思ったより時間が掛かり、少々後悔し始めた頃いきなり目の前に朱の楼門が現れた。五時を回っていたので楼門は閉ざされ、本殿への参拝はかなわなかった。外から参拝を済ませ神橋を渡ると空には、まんまるお月さんがかかっていた。日暮れが遅くなったものである。周りはまだ薄明るく、月は白かった。我々は懇親会場へと足を速めた。 < 尾崎喜美子・記 > |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright ©2025 BASHO-meeting. All Rights Reserved. | このサイトについて |
サイトポリシー |